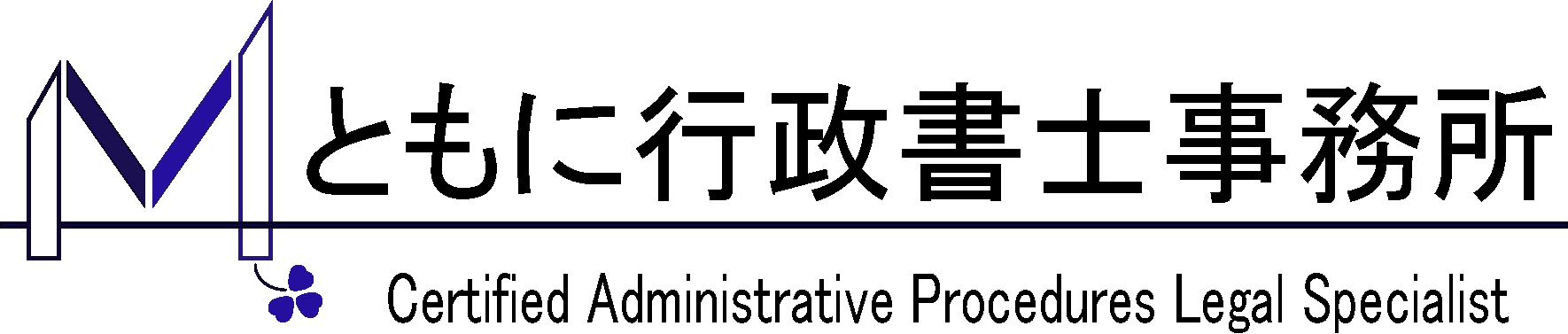| 岡山市・倉敷市・玉野市で相続手続きをサポートする行政書士が、遺産分割協議書の作成手順や費用についてわかりやすくご案内いたします。 遺産分割は、ご家族の絆を守り、将来の安心を築くために欠かせない大切な手続きです。 しかし、話し合いがこじれると「争続(そうぞく)」に発展し、解決までに多大な時間や労力、そして精神的な負担がかかることもあります。 特に対応が遅れるほど、親族間の感情的な対立が深まり、冷静な話し合いが難しくなる傾向があります。 こうした事態を防ぐためにも、早めにご相談いただくことが安心につながります。 実際の遺産分割では、感情や価値観の違いから話し合いが長引くケースも少なくありません。 当事務所では、家庭裁判所の家事調停委員として遺産分割調停に携わる行政書士が対応いたします。 ご家族の思いに寄り添いながら、冷静かつ公平な立場から、円滑で実効性のある遺産分割協議書の作成を丁寧にサポートいたします。 |
対応地域
| 岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 |
その他の地域の方も、どうぞお気軽にご相談ください。
相続財産となるもの
相続財産となるのは、単に「物」や「お金」だけではありません。
故人(被相続人)が持っていたすべての権利と義務が、相続の対象となります。
| 区分 | 種類 | 内容例 | 補足事項 |
|---|---|---|---|
| プラスの財産(積極財産) | 有形資産 | 土地・建物、自動車、貴金属、骨董品、家具など | 評価額の算定が必要(不動産鑑定・査定など) |
| 金融資産 | 預貯金、現金、株式、投資信託、保険解約返戻金など | 金融機関への照会が必要な場合あり | |
| 権利関係 | 貸付金、売掛金、特許権、著作権、借地権など | 契約書や登記簿等の確認が重要 | |
| マイナスの財産(消極財産) | 債務 | 銀行借入、住宅ローン、クレジットカード残高、未払い医療費など | 相続放棄や限定承認の検討余地あり |
| 保証債務・義務 | 故人が保証人であった債務、損害賠償義務など | 保証債務は相続人が法定相続分に応じて承継します。ただし、債権者は相続人のうち誰か一人に対して全額を請求することができます。 |
- 遺産分割における「財産評価」の重要性
相続財産は、税法上の評価(相続税を計算するための評価)が行われますが、これとは別に、遺産分割協議のためにも評価が必要になります。
- 遺産分割協議で評価が必要な理由
遺産分割協議の目的は、「相続人全員が、どの財産を、どれだけ受け取るか」を決めることです。公平に分けようと思えば、当然ながら「それぞれの財産の価値」を把握しなければなりません。
全員が納得するなら、市場価格と異なる評価額を適用することも可能です。大切なのは、相続人全員がその評価に同意し、将来的に争いが生じないことです。
協議を円滑に進めるためにも、客観的な評価を土台にしつつ、ご家族の事情を考慮した柔軟な評価の合意を目指すことが重要になります。
被相続人死亡後の流れ
- 被相続人に対する事務的な手続き
| 手続き内容 | 期限の目安 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 | 市区町村役場へ提出 |
| 健康保険に関する手続き | 国民健康保険は14日以内 | 自治体によって異なる場合があるため、事前に手続き先の市区町村役場に問い合わせ ※死亡届を提出すれば、国民健康保険資格喪失届は不要な場合あり 会社員は事業主が手続き:事実発生から5日以内 |
| 公共料金・各種契約の名義変更 | できるだけ早めに | 電気・ガス・水道・電話・クレジットカード等 |
| 公的年金に関する手続き | 14日以内(厚生年金は10日以内) | 年金事務所や市区町村役場へ届出 |
| 被相続人の所得税の準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 | 税務署にて申告 準確定申告は必ずしも全ての方に必要なわけではありません。被相続人の所得や状況によっては申告が不要となる場合もあります。 |
| 生命保険金の請求(加入している場合) | 請求期限は3年(簡易保険は5年) | 保険会社へ請求 保険会社の約款によっては5年など異なる場合あり |
- 遺産相続に必要な手続き
| 手続きの段階 | 内容 | 補足事項 |
|---|---|---|
| ① 遺言書の確認 | 遺言書の有無を確認 | 遺言書を発見した場合家庭裁判所の検認が必要 ただし、以下のものは家庭裁判所の検認が不要 ・公正証書遺言 ・法務局で保管されている自筆証書遺言 |
| ② 相続人の確定 | 戸籍調査により相続人を確定 | 依頼により弊所で調査 |
| ③ 相続財産の調査 | 預貯金・不動産・株式・借金等を調査 | プラスの財産・マイナスの財産両方を確認 依頼により弊所で調査 |
| ④ 相続放棄・限定承認の検討 | ・単純承認(すべて引き継ぐ) ・限定承認(プラスの範囲でマイナスも承継) ・相続放棄(すべて放棄) | 限定承認と相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述 |
| ⑤ 遺産分割協議 ※遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。 | 相続人全員で分割方法を話し合う | 協議が成立すれば「遺産分割協議書」を作成 依頼により弊所で作成支援 |
| ⑥ 協議不成立の場合 | 家庭裁判所にて調停・審判 | 裁判所の関与により分割を決定 |
| ⑦ 財産の名義変更 | 不動産や預貯金等の名義を変更 | 不動産の相続登記申請は義務化(2024年4月以降) ※所有権の取得を知った日から3年以内 預貯金等の名義変更は依頼により弊所で支援 |
| ⑧ 相続税の申告・納付 | 被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内 | 基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合は2人まで 取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません ※個別の税務相談は税務署または税理士へ |
遺産分割手続きの種類
- 手続き方法
遺産分割の方法は、大きく分けて以下の4つのステップがあります。
原則として、上の方法から検討し、合意に至らない場合に次のステップへ進みます。
| 手続き方法 | 内容 | 補足事項 |
|---|---|---|
| ① 遺言による分割 | 被相続人が遺言書で指定した分割方法に従って分割します。 | 原則として相続人同士の話し合いは不要で、最も手続きがスムーズかつ迅速です。遺言書の内容に基本的に従うため、安心感をもって進められます。 |
| ② 協議分割(遺産分割協議) | 遺言がない場合や、遺言と異なる分割をしたい場合に、相続人全員で話し合い、自由に分割方法を決定します。 | 自由度が高く、財産や状況に合わせて柔軟な分割が可能です。全員の同意が得られれば、後の手続きに不可欠な遺産分割協議書を作成します。 |
| ③ 調停分割 | 相続人同士の話し合い(協議)がまとまらない場合に、家庭裁判所の調停を利用します。 | 調停委員が中立の立場で間に入り、話し合いをサポートします。最終的な決定は相続人の方々の合意に基づき行われ、合意内容は調停調書として作成され法的効力を持ちます。 |
| ④ 審判分割 | 調停でも合意に至らない場合に、裁判官が相続財産や各相続人の事情を考慮し、審判で分割方法を定めます。 | 最終的な決定権は裁判官にあり、相続人の合意は不要です。審判の結果に不服がある場合には、高等裁判所に対して「即時抗告」の申立てが可能。 |
- 分割方法
実際に遺産分割を行う際、一つの方法だけで解決することは少なく、複数の方法を組み合わせて「公平さ」と「利便性」を両立させることが一般的です。
組み合わせ例:当事務所では、現物分割 + 代償分割が最も多いパターンかと思います。
方法: まず、不動産や株式などの主要な財産を個々の相続人に割り振る「現物分割」を行います。その結果、相続分以上の財産を取得した相続人が、差額を現金(代償金)で他の相続人に支払う「代償分割」で調整します。
使用されるケース: 自宅などの不動産を売却せずに特定の相続人に引き継がせたいが、他の相続人にも公平な取り分を確保したい場合。
ポイント: この方法を使えば、「実家を残す」という目的を達成しつつ、現金のやり取りで金銭的な公平性を保てます。
| 分割方法 | 内容 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産そのものを個々の相続人に割り振る。 | 最も手軽で手続きが簡単。 公平な分割が難しい場合があるため、代償分割と組み合わされることが多い。 |
| 代償分割 | 取得分を超えて取得した相続人が、他の相続人に現金(代償金)を支払う。 | 不動産などを売却せずに残せる。 代償金を支払う側の現金が必要。 現物分割後の調整としてよく利用される。 |
| 代物分割 | 取得分を超えて取得した相続人が、他の相続人に自身が持つ現物を譲渡する。 | 代償金の現金を準備しなくて済む。 譲渡される「代物」の評価やニーズが問題になる。 |
| 換価分割 | 財産をすべて売却して現金に換えてから分割する。 | 公平で明確な分割ができる。 思い入れのある財産を手放す。 売却費用や税金(譲渡所得税等)が発生する場合がある。 |
| 共有分割 | 不動産などの財産を、複数の相続人が共同で所有(共有)する。 | 一時的に手軽に分割できる。 将来の売却・管理が非常に困難になりやすく、問題の先送りになりがち。 |
遺産分割協議書の作成支援
上記遺産分割手続きの種類の中にある、手続き方法②が該当します。
有効な遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産分割が行われます。
ただし、遺言書に財産の「割合」だけが記されていて具体的な分け方が不明な場合や、遺言執行者が指定されておらず手続きが進められない場合などには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となることがあります。
遺産分割協議に法的な期限はありませんが、相続税が発生する場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に分割を終えておく必要があります。
また、預貯金の名義変更や不動産の登記手続きには、遺産分割協議書の提出が求められることがあります。
- 遺産分割協議書の作成支援に加えて相続手続きのサポートもお任せ下さい
相続手続きは、
・役所や金融機関への複数回の訪問
・戸籍や残高証明などの書類収集
・書類の記載・提出方法の確認
など、時間と労力がかかる煩雑な作業が伴います。
特に、年配の方やお仕事でお忙しい方にとっては、大きな負担となることも少なくありません。
そこで弊所では、
・ 預貯金の名義変更
・ 不動産登記に必要な協議書の作成
・ 相続人間の調整支援
など、相続人への名義変更に関する手続きのサポートを行っております。
※対応可能な手続きに限ります。専門性が必要な場合は、信頼できる司法書士・税理士・弁護士等をご紹介いたします。
- まずはお気軽にご相談ください
「何から始めればいいかわからない」
「相続人どうしの話し合いが進まない」
「銀行や役所に行く時間が取れない」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご家族の大切な財産を、円満かつ確実に引き継ぐために。
あなたの状況に合わせた、サポートを心がけています。
費用
当事務所では、以下の業務を基本セットとして承っております。
遺産分割協議書の正確性と実効性を確保するため、原則として3業務を一括でご依頼いただいております。
基本業務セット
| 業務内容 | 費用(税込) | 補足事項 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書の作成と支援 | 66,000円~ | 内容・相続人の数により加算あり ※実費別途 |
| 相続人の調査 | 基本報酬(配偶者・子が相続人となる場合) 33,000円 兄弟姉妹が相続人となる場合(人数別) 55,000円~ 明治期まで遡る相続人調査(特別調査) 110,000円~ ※兄弟姉妹相続・代襲相続を含みます ※調査範囲が著しく広範な場合は、事前にご相談・お見積りいたします | 戸籍収集・関係図作成等を含む ※実費別途 |
| 相続財産の調査(財産一覧表作成) | 33,000円~ | 不動産・預貯金等の確認を含む ※実費別途 |
その他関連業務
| 業務内容 | 費用(税込) | 補足事項 |
|---|---|---|
| 戸籍・住民票等の取得代行 | 3,300円/件 | 対象の役場ごと/件 ※実費別途 |
| 被相続人宅以外の財産調査 | 3,300円~/件 | 対象の役場ごと/件 ※実費別途 距離により加算 |
| 銀行・車などの名義変更支援 | 33,000円~/銀行1支店ごと | 証券会社1社ごと:33,000円~ 車(相続):33,000円~ 難易度により加算 ※実費別途 |
お支払いについて
- 業務着手時に、初回のお支払いをお願いしております
- 残金は業務完了後に、合意済みの金額に基づいてご請求いたします
- 業務の過程で追加費用が必要となる場合は、事前にご相談・ご同意をいただいたうえで進行いたします
- 事前のご相談・ご同意なく、費用が加算されることはございませんのでご安心ください